

Access: |
アラカルト寺澤勉先生の思い出今日は雛祭りですが、すみません。訃報のお話しです。学会からのメールで、ずっとお世話になってきた寺澤勉先生が2月13日にお亡くなりになっていたことを知り、大変ショックを受けています。心よりご冥福をお祈りいたします。先生のご業績として知られているのは、東京モーターショーの計画や研究に長年関わられてきたことです。一時代前、東京モーターショーは日本一集客があった巨大イベントで、いかに混雑を緩和するかなどを展示工学的視点から研究され、実践に生かされていました。ディスプレイ関連の協会や学会でも活躍され、私も日本展示学会の事務局や学会誌編集、あるいは展示学事典を編纂する際に大変お世話になりました。また、20年ほど前、うちの大学に文化政策学部ができたとき、大学と京都文化博物館を会場に研究大会を誘致したのですが、京都まで来て下さりエールを送っていただきました。自分に厳しく人に優しい人格者でした。やさしい笑顔しか思い出せません。ただ、拓殖大学時代にちょっと頑張り過ぎてしまって、一時ご病気をされ、その後復帰されましたが、この数年はコロナもあってお目にかかれていませんでした。とても残念です。私はその後公共政策に軸足が変わってしまいましたが、少しでも先生の研究を次に繋げられたらと思います。
参考:寺澤勉先生のご業績(千葉大学のサイト) http://design-cu.jp/sakuhin_web/ta/terazawa_tsutomu/index.html 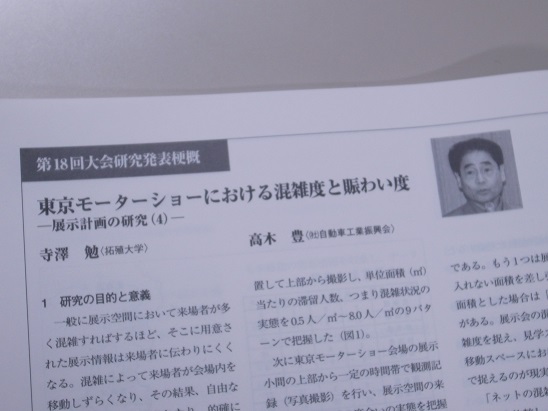 │-│-│2022/03/03(木) 21:14│
アラカルト研究倫理と研究道徳芸術文化交流を契機に、1971年に京都市とキエフ市は姉妹都市を提携していたということを今日知りました!京都市は今日から市役所前に献花台を設置し、また各役所の窓口や地下鉄の駅で寄付金を募っているとのことです。◆今日はずっと遠隔で会議や研修がずっと続き、なんかぼんやり。コンプライアンス研修会というのがあり、面白かったのは民俗学研究が事例に上がったことです。私が学生の頃はほとんど研究倫理という制度がなく、民俗学の場合、地域全体が丸裸になってしまうため、その後調査方法が大きく変わったと思います。とくに族制調査は個人情報を聞き出さないと記録がとれないので、最も難しい領域になっていると思います。でも、当時から調査方法だけでごっつい本があり、それをみっちり勉強し、ヒアリング項目もきちんと設計してからフィールドワークを行っていました。ヒアリングの場合、慣れない人がやると誘導尋問になりやすいため、その点はとくに気をつけたりしていたのを思い出しました。写真は昭和60年に調査した報告書で、私の代で編集したものです。この頃はまだ基本を学ぶだけで精一杯でした。ただ、内容は本格的なものなので、報告書をまとめるのに4年かかりました。つまり卒業してからもずっとやっていて、この挿絵や表紙の切り絵は、私がデザインしたものなので愛着があります。翌年の調査は後輩が編集したのですが、結局6,7年かかったんじゃないかなぁ。ちなみに、同期の友人は埼玉県川口市の学芸員となり、後輩は大分県博の学芸員をしています。二人とも民俗が専門です。代々、誰かが教員か学芸員になっています。その後の研究会では、調査が難しくなっていくのと、報告書をまとめる労力もあり、悉皆調査を大学生が行うことはほとんどなくなりました。ただ、柳田国男先生とその秘書であり学部創設者の鎌田久子先生が創設と運営に関わった研究会でしたので、いまでも存続はしていますが調査活動は十分できていません。学生の頃は、今以上に地域に課題があり、当時は試行錯誤ながらもそれを肌で感じられたことが、今の地域研究に生きているように思います。それから、共同研究の場合は、どうしても分担や編集等でトラブルになりがちなので、私の場合、大学での研究は単独調査を基本としています。とにかく、不正するというのは論外で、また研究成果も大事ではあると思いますが、それ以上に対象者のメリットを少しでも考えることが重要だと思います。情報を取るばかりでなく、何をお返しできるかということ。研究倫理は当然ですが、それ以上に研究道徳を持つように心がけてはいます。たいしたことはできていませんが、研究情報をなるべく公開するようにしているのは、実はその一環でもあります。
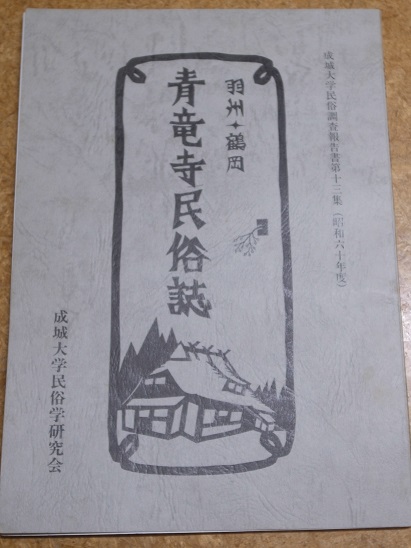 │-│-│2022/03/02(水) 21:49│
アラカルト人類は繁栄するのか、それとも破滅の道を進むのか同じ地球上で堂々と戦争が行われているのに、身のまわりでは普通の日常が続いているという、不思議な環境が生まれています。もう一つ不思議なのは、ネットの世界です。日本ではトヨタなどの企業サイトがロシアに絡むとみられるハッカーにサイバー攻撃されたかと思えば、アノニマスと呼ばれる国際ハッカー集団がロシア国防省などをハッキングしたという。もはや、戦争もリアルの世界からヴァーチャルの世界に広がっていて、見えないからこその不安を感じます。今後、人類は繁栄するのか、それとも破滅の道を進むのか。◆ところで、今朝の日経新聞に小田原の「すどう美術館」に関する記事が出ていました。美術にまったく縁のなかった普通の会社員が、洋画家・菅創吉氏のある一つの作品に出会ってから、その後個人で美術館まで作ってしまうというお話し(詳しくは新聞をご覧下さい)。昨日の細見美術館も個人コレクションですが、日本にはこうした施設が多数存在します。小田原はよく行ったりしますが、実は記事を読むまでこの施設についてまったく知りませんでした。現在は、同志だった奥様の追悼展を開催中とのこと。次回行くときはぜひ寄ってみたいと思いました。願わくば、争いとともに生きるのではなく、文化・芸術とともに生きたいと思います。
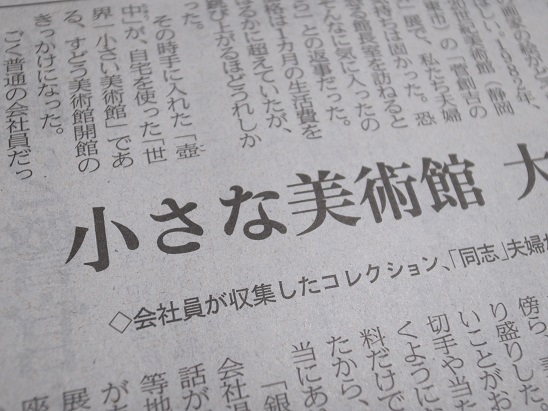 │-│-│2022/03/01(火) 22:14│
アラカルト環境デザインというアプローチ昨夜は急に強い偏頭痛になり、そのまま寝込んでしまいました。今はほぼ治りましたが、今日は比較的大人しくしていました。◆ところで、昨日ですが、約束があったので久しぶりに山を越えて岡崎へ。細見美術館で根来(漆器)の展示を鑑賞してきました。何度も行っていますが、改めて素敵な美術館だと思いましたが、この日は男3人での入館という。今の経営者や政治家には、この細見家の審美眼を学んで欲しいところです。よくここまで集めたものです。岡崎には、ここ以外にももの凄いコレクションが随所にあります。有隣館も久しく行っていない…藤井館長からは熱烈な年賀状を頂いていたので、今度行こう。このところ天気が良く、日中はコートがいらないくらいです。岡崎も景観が綺麗です。山科も電柱を埋設してほしいし、親水空間もなんとかしないと。公共政策において空間デザイン・環境デザインという観点が不十分ということは何十年も前から指摘していますが、なかなか浸透しません。そうこうするうちに、文化政策や都市環境デザインという、うちの学科名も消えてしまった。まぁ、死んだわけではないので地道にがんばります。
 │-│-│2022/02/28(月) 21:23│
アラカルト人はなぜ同じ過ちを繰り返すのか人はなぜ同じ過ちを繰り返すのか。ウクライナ出身でチェルノブイリ原発事故も経験されているバンドゥーラ演奏家のナターシャ・グジーさんが、2008年8月6日にNHKの「視点・論点」で「いつも何度でも」(ジブリ映画「千と千尋の神隠し」の主題歌)を演奏したもので、その思いが伝わります。私は深刻な問題があると、たまにこの映像をみます。その後、福島の原発事故が起こり、今回まさか彼女の故郷が再びこのような事態になるとは夢にも思いませんでした。我々ができることは少ないですが、歌を歌い祈ることはできます。それが芸術の力。著作権に問題はありますが、多くの人にこの映像を見て欲しいと思いました。
<ナターシャ・グジーさんの魂の演奏> https://www.youtube.com/watch?v=d4Kijkkz4f0 │-│-│2022/02/27(日) 08:46│
|