

Access: |
アラカルト縄文の衝撃天候のせいか、朝からすっきりせず。でも仕事はいっぱい。リモートの添削もドッサリ。私は一人一人丁寧に添削文を書きます。そうとうな時間がかかります。ただ、これはやりたいからやっています。また、対応したくなる課題を出すようにしています。◆ところで、昨日、ユネスコの諮問機関が「北海道・北東北の縄文遺跡群」を世界文化遺産に登録するよう勧告したとのこと。とてもおめでたいことです。記紀によって東北の文化は葬り去られたわけですから、記録の残忍性、また皇国史観の罪を改めて思います。我々の世代はそれに染まっていました。まさに洗脳。私が古代や東北にとくに関心をもったのは、2011年の震災以降、東北地方の博物館や史跡に足を運び、様々なものを見たからです。とくに衝撃を覚えたのが、写真の「垣の島遺跡」(北海道函館市)の「漆糸製品の復元」を記録した報告書を見たときでした。この資料は宝物の一つです。この遺跡から、9000年前の漆製品が発掘されたのですが、なんとそれは「漆の糸」なのです。漆といえば漆器ですが、9000年も前に糸に塗られていたとは最初信じられませんでした。縄文時代といえば、粗末な衣装を着ているとばかり勝手に思っていましたから。この漆糸製品がいかに手間をかけて作られているかを知れば、縄文人の文化・芸術がどれほど高かったのかが良く分かります。恐らく、知能的には我々より上だったかも知れません。また、「御所野遺跡」(岩手県一戸町)の復元住居を見たときも、目からウロコでした。「竪穴式住居=古くさい住居」くらいにしか思っていませんでしたが、この建築は地震に強く、電気がなくても寒い冬を過ごせるスーパーアーキテクチャーだと分かったときは、無駄にエネルギーを浪費する現代人の愚かさを思い知りました。ちなみに、この遺跡の復元住居は東日本大震災時に倒壊したものはありません、一方で現代住居は沢山壊れました。なので、その後、古代の文化に強い関心を持つようになったのです。世界遺産をきっかけに、遺跡を単に過去のものとするのではなく、当時の思想や文化を今にどう生かせるのかを考えていくことに繋がればと願います。
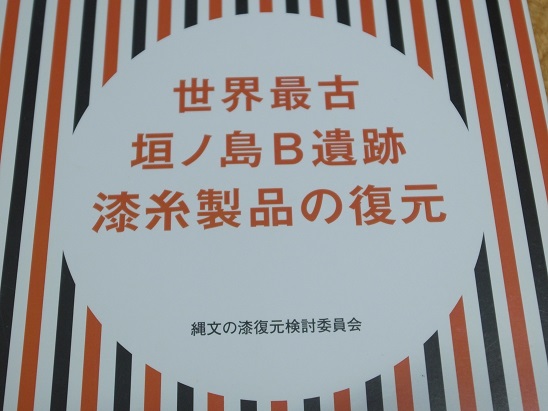 │-│-│2021/05/27(木) 23:00│
アラカルト鏡王女を想う今夜は皆既月食とスーパームーンが同時に見られる特別な日のようで、学生たちが興味深く語っていましたが、京都は生憎の曇り空。心の中でイメージすることにしましょう。◆ところで、一昨日安土に行きましたが、途中必ず通るのが竜王町です。なぜかこの地に惹かれる神社があります。それが鏡神社です。とても小さく参拝する人もほとんどおりませんが、ちょっと早めに到着したので、役場に行く前に参拝してきました。社殿はとても堂々としています。ご祭神は天日槍(アメノヒボコ)。この神は渡来神で、新羅(しらぎ)の国の王子だという。本当にここに来たのかどうかは不明ですが、関係者がこの地で鏡作りに携わったとしてもおかしくありません。この鏡氏の出身者が鏡大王(かがみのおおきみ)とも。彼女は、後に藤原(中臣)鎌足の妻となり、鎌足が病気の時に祈願所として建立したのが山階寺(やましなでら)であり、今の奈良興福寺の前身です。この山階寺の推定地は、今私が住んでいるマンションのすぐ近くですので、彼女もかつてはうちの辺りにいたのかも知れません。ただ、なんというか、鏡大王は新羅と関わり鎌足は百済(くだら)と関わります。その辺の半島との力関係がよくわららず、いつも古代史は複雑だなぁと思います。1300年以上も前の話ですが、満月の日に大王を想ってみます。ただ、今日の1回生ゼミでたまたま韓国の話になったので、「百済って知ってる?」と聞いてみたら誰も知らず、思わずずっこけましたけど…なので、なぜ「日本」という国ができたか、また日本人といっても多くの外の血が入っていることをちょっと説明しておきました。
 │-│-│2021/05/26(水) 21:26│
アラカルト好循環のまちづくり日中はいいお天気でしたが、夕方から強烈な風が吹き始めました。花粉か黄砂かわかりませんが、一時鼻水がとまらなくなりました。このところ気候が荒れているので、気持ちくらいは落ち着いていたいものです。◆ところで、最近読んだ本の中でとくに良かったのが、枝廣淳子さんの『好循環のまちづくり』(岩波新書)です。先月発行されたばかりの新書。とても読みやすく、「まちづくりハンドブック」的な構成になっています。もともと翻訳家だったようですが、その後地域政策に関わり、有名なところでは、島根県・海士町の町おこしや、徳島県・上勝町のゼロウェイスト政策(ゴミを出さない政策)を指導されています。両方ともいつかきちんと調査をしたいと思っていたので、その舞台裏を知れてとても有意義な内容でした。やはり実践家の文章は説得力があります。かなり「腑に落ちる」本でした。一度お会いしたいです。この方は環境政策には強いのですが、文化政策的な視点がほとんどないのが残念でしたが、それぞれの得意分野を生かす政策を考えれば良いのだと思いました。ただ、それでも地域の二極化は止められないでしょうねぇ。
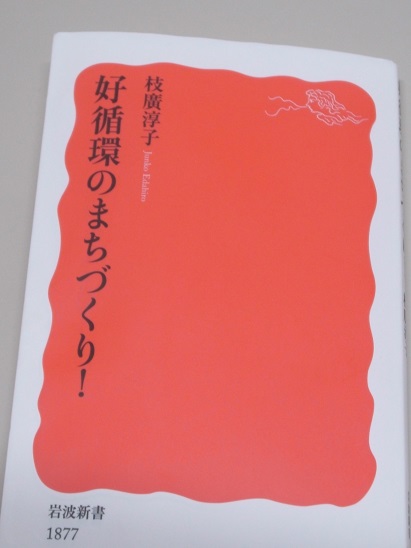 │-│-│2021/05/25(火) 21:57│
アラカルト地域を変える連携授業日によってコロコロ陽気が変わりますね。でも、このところ湿気がましなので助かります。◆今日は朝から近江八幡市の安土支所へ。今年度から本格的に地域振興の授業で関わることになったのですが、新型コロナの影響で特別授業ができなくなったため、現地で映像収録をすることにしたのです。収録だけでなく様々な打ち合わせも行ったので、結果的に3時間もかかってしまいました。移動も合わせれば、これだけで5時間の作業…うまく撮れているといいのですが…。なんだか、最近自分のやっていることは完全に映像プロダクションの仕事です。メチャクチャ手間と時間がかかるので、ほんとはやりたくありませんが、やるからには中途半端が嫌いな私。机上の空論ではなく、共に地域を変える連携授業を目指します。一応、プロジェクト名も考えたのですが、笑われそうなので当面ヒミツです。
 │-│-│2021/05/24(月) 22:12│
アラカルト人間のエゴと真実久々にいいお天気だったのでお出かけしたかったですが、我慢してお家時間としました。今日はちょっと念入りに車の手入れをしました。エンジンルームをクリーニングしたり、錆びている箇所に転換剤を湿布したり、塗装の剥げを塗り直したり。宣言が終わったら思いっきりドライブしたい。◆夜にDVDをレンタルして、前から見たかった「ワンダーウーマン1984」を鑑賞。なんだか、タイムマシンに乗ったような不思議な感覚でした。スミソニアンの博物館群が舞台になっているところも良かった。1980年代というのはハリウッド映画全盛期で、まだ家にビデオもなかったと記憶しています。美術セットも凝っていて、モールでの撮影は、映画「コマンド−」(1985年)を思い出しました。この頃はまだ、パソコンもインターネットも普及しておらず、もちろんスマホもありません。マイコンやオフコンの時代。それに、冷戦をありありと思い出しました。日本でも真剣に核シェルターを作る動きなんかもあったんですから、深刻でしたね。映画は、女性版スーパーマンみたいな内容ですが、テーマは「人間のエゴと真実」といったところでしょうか。誰しも願望はありますが、それが強くなりすぎると「争い」が起きてしまいます。それを少し強調したような感じ。主演のガル・ガドットさんははまり役で有名になったようですが、もともとイスラエル人。最近、またパレスチナとの対立が激化しましたが、原因はそれぞれの宗教が他の宗教を認めないというエゴから来ています。平和を実現するためには、エゴを捨てさえすればいいのですが、教義が邪魔をしてそれができません。唯一神を崇める宗教がある限り、残念ながら互いに認め合うという環境はまず生まれません。そういう意味で、宗教を習合していくような日本人の信仰観というのは特殊だなぁといつも思います。
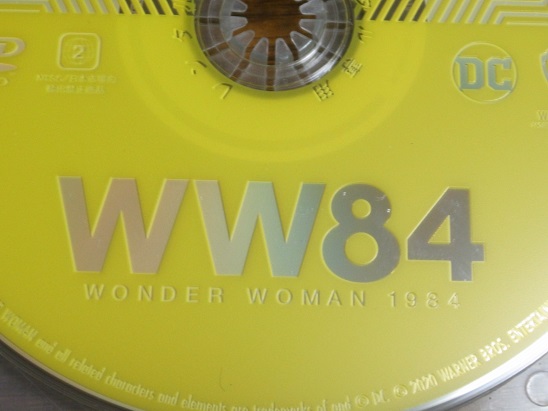 │-│-│2021/05/23(日) 23:43│
|