

Access: |
アラカルト水出し茶〜記録更新やっと週末。今週もいろんなことがありすぎて何しているのかよくわからなかったり。遠隔授業の課題添削も、学生以上にコメント書いていたりして。根詰めないよう、気をつけたいです。◆前に知人から頂いたお茶をこのところずっと飲んでいるんですが、これが結構美味しいんです。また、小袋に入っているので、コップにぽんと入れてしまうだけ。茶葉の処理も簡単で有り難い。先週まではお湯を注いでホットで飲んでいましたが、さすがに暑いので冷たい水を入れてみたら、ちょっと時間はかかりますがちゃんと染まって飲めました。2杯くらいは十分行けるので、最近午後タイムはこのほうじ茶を飲むことが多いです。そういえば、今年は信楽に行ってないなぁ。最近、甘いものも継続的にひかえているので、体重減もまた記録を更新しました☆今月はあともう1キロ減に挑戦します。
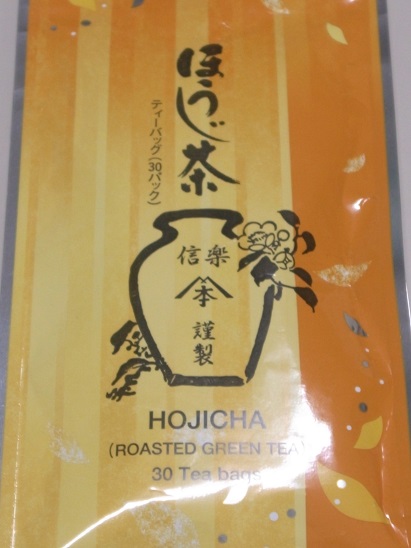 │-│-│2021/06/11(金) 21:38│
アラカルト車業界と車文化の未来連日暑い日が続きますが、まだ扇風機も出さず扇子だけで凌いでいます。この時期はできるだけ体を自然に慣らすようにすると、風邪をひきにくくなるのです。◆ところで、最近読んでいた本がこれ。先月発売になったばかりの『日本車は生き残れるか』(桑島浩彰・川端由美、講談社現代新書、2021)です。衝撃的なタイトルですが、内容的には車産業の現況について俯瞰的にまとめられているものです。10年前からわかっていたのに、こういう本がほとんどなかったような気がします。とくに欧米や中国の動向についての整理は、変化が早いだけにありがたいです。もう一歩の深さがほしいところではありましたが。車産業に限らず、今は産業界全体で急激な構造変革の節目にあるように思います。どのような企業が生き残るのでしょうか。本書にあるように、車はどんどんスマホ化していくのでしょうけれど、私は車産業の未来や自動運転車自体にはあまり興味ありません。むしろ車文化についてはとても関心があり、産業構造の変革が文化にどのような影響をおよぼすのかを考えながら読んでいます。この本でも、結局車業界全体がデザイン思考から抜け出せていないことがわかりますし、そもそも車好きな人は運転自体が楽しいわけであって、自動運転車が欲しいとは思わないでしょう。そうした別の視点がゼロな点が課題だと思いましたし、実はそこにこそニッチな文化が生まれそうな気がしています。今から予測しておきますが、今後本書のようにEVや水素が主流になっていくのは間違いないですが、一方で旧来のエンジン技術は変化をしながらも生き残っていくと考えています。ナンバーワンではなく、オンリーワンを目指す企業があってもいいし、カーボンニュートラルの仕組みは多様です。これからも複眼的に観察していきたいと思います。ちなみに、これは仕事ではなく、あくまで趣味の延長です。◆後ろ2枚の写真は学内のお花たち。とってもかわいいです☆
 │-│-│2021/06/10(木) 21:27│
アラカルト紫陽花手水この暑さは金曜日くらいまで続くようです。しばらく気をつけましょう。今日もいくつかの会議がありましたが、このところずっとリモート。未だに慣れません。学生からも「対面がいい」「学校は勉強するだけの場ではない」との意見を今日も聞きました。うちは今でも5割を対面にしているのでまだ良いですが、ずっとリモートの学生は辛いでしょうね。ワクチンは本当に救世主となるのでしょうか。◆仕事終わりに、いつもの藤森神社に御神水を汲みに行ったら、「紫陽花まつり」が始まっていました。でも16時で閉めてしまうので、入れませんでした。また、機会を見つけてゆっくり鑑賞したいと思います。今日は手水鉢に浮かぶ紫陽花を撮影しました。いつもと雰囲気が違っていて、まさに華やかでした☆
 │-│-│2021/06/09(水) 21:45│
アラカルト伝統工芸の新たな継承方法だんだんと学内関係者の親族がワクチン接種をしたという話を聞くようになりました。ただ、面白いのは「打ってほしい」という人と、「打ちたくない」という人に分かれる点です。私はそもそも注射が嫌いなので「打ちたくない派」ですが、仕事上打っておいた方がいいんでしょうねぇ。◆火曜日はゼミの日です。3回生ゼミのテーマがほぼ確定し、少しずつ内容を深めています。今日学生と話していて面白かったのは、誰も「計画的陳腐化」の言葉を知らなかったこと。マーケティングの授業等で習わないのだろうか。人々は企業が画策する流行に乗り、モノを買いサービスを受け、そして古いと思わされてすぐに捨てる。その繰り返しで企業の業績はアップしますが、資源ロスは止まず日本中ゴミだらけになっていくわけです。最近のプロダクトは、壊れるように設計され、意図的に陳腐化されていきます。この学年では、昨今のSDGsとからめながら、その悪循環を止めるためのプロダクトを伝統工芸とからめて提言していきます。ただ、抽象的な話だけでは理解しにくいので、具体例を示していきます。例えば、いつも私が使っている筆ペンがあります。日常的に本格的な筆を使うのはなかなか難しいですが、筆ペンなら気軽に使えます。しかも、墨がカートリッジ式になっているので万年筆のように永遠に使えますし、墨がインクのように固着しないので万年筆よりも優れていると思います。本体には竹工芸が使われ、入れ物には伝統的な布地が使われています。プロダクトのクオリティが高いのです。買ってから恐らく10年以上経過していると思いますが、まったく問題ありません。まさに「一生モノ」です。少々高くても、長く使うことで結果的に安くつく場合もあります。伝統工芸といっても、使われなければどんなに良いモノでも継承は難しくなります。本職の方からは「邪道」といわれるかも知れませんが、可能な範囲で時代に合わせることが大事だと考えますし、それをどうプロダクトし、デザインするかが課題なのだと思います。結構好きなテーマなので、京都の伝統工芸を勉強しながらいろんなアイデアを考えてみたいと思います。
 │-│-│2021/06/08(火) 22:12│
アラカルトクリエイティブ人材の必要性ニュースによれば、今日の京都は32.6度だったとのこと。完全に真夏日ですね…。日中、実習関連の所用で町中を運転していたら、途中で気分がすぐれず、しばらく休んでいたら復活しました。あぶないあぶない。明日も暑くなるようですので、熱中症には気をつけましょう。◆ところで、今朝の日本経済新聞に「博物館法改正」に関わる記事が掲載されていました。今回は大幅改正を考えているようで、気になります。先週、大学にもアンケート用紙が回ってきたので回答したばかりです。「質」を高めようとしているようですが、実は質にもいろんな側面があります。単に研究力を向上させようとしても、この時代にそぐわない可能性があり、危惧しています。研究力は活動のベースとなるもので、その質を高めること自体に異論はありませんが、それだけではまったくダメだと思っています。一方で、京都市に代表されるように、自治体の財政は新型コロナの影響で今後さらに深刻になっていく所も増えていくでしょう。また、2008年改革でうちの大学では資格履修者が半減以下となり、大学によっては講座そのものをやめていく割合が増えるようにも思われます。施設の役割や必要性に対する概念そのものがもう古くなっていると考えていますし、そもそも取得単位が増えかつ就職できない資格に人は集まりませんので、職員を増やす政策がセットでなければなりません。加えていうなら、今本当に求められているのは「クリエイティブ人材」であると私は考えています。博物館の持つ資源を利用して社会課題に対応した新たな事業創造を担えたり、事業予算(外部資金)そのものを獲得できるスタッフを揃え、様々な事業を展開していかないと、生き残れないのではないでしょうか。展示をして人を待っているような時代はとっくに終わっていると思っています(それ自体が必要ないという意味ではありません)。このことは、文化政策だけに限りません。日本の基幹産業全体にも政治にも創造性がかなり欠けているように思えてなりません。うかうかしていると、次世代のインフラの多くを海外に奪われてしまうかも知れません。私自身としても、社会課題や地域連携に貢献しない施設などまったく眼中にありません。少子高齢化が待ったなしの現在、まちそのものが成り立つかどうかという時代ですから、それらに命がけでコミットしている組織に着目していく予定です。
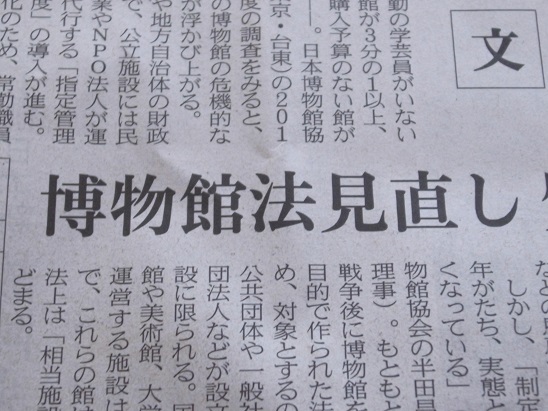 │-│-│2021/06/07(月) 22:01│
|