

Access: |
アラカルト松方幸次郎の魂東京は酷く暑かったけれど、京都戻ったらかなり涼しい、というか寒い。今日は自由見学でしたので、東京のいくつかの施設を回りました。細かくは後日アップしますが、今日は国立西洋美術館について触れておきます。どうしても見たかった「松方コレクション展」に行ってきました。西洋美術館は、実業家であった松方幸次郎(まつかた こうじろう:1866年〜1950年)がヨーロッパで収集したコレクションが母体となっています。開館60周年を記念して開かれている展示会なのです。一般にはあまり知られていないかもしれませんが、日本の芸術振興に大きな足跡を残された方です。洋画に限らずヨーロッパに渡った浮世絵も含めると約1万点もの作品を収集。しかし、震災や戦災、事業の失敗等で多くが焼失・散逸・接収・売却されたのですが、戦後フランス政府から返還された作品が母体となり、美術館が建設されました。残念ながら美術館を見る前に彼は他界されています。今回の展示は海外に残された作品達も加わっていて、松方さんが生きていたらさぞ喜んだことでしょう。彼の魂を見る思いで、館内を歩いていたら涙が出てきました。また、展示には2016年にパリ・ルーヴル美術館でボロボロの状態で発見され、その後国立西洋美術館に寄贈された松方コレクションの一つ「モネの《睡蓮、柳の反映》」が修復を経て、初めて公開されていました。家に帰ったら、その修復プロジェクトがNHKスペシャルで取り上げられていたので、タイムリー過ぎて驚きました。まだ読んでいませんが、このコレクションが誕生するドラマを描いた原田マハさんの新刊本を美術館のショップで買ってきました。また、ゆっくり読んでみたいと思います。
 │-│-│2019/06/16(日) 23:04│
アラカルト問題の本質朝から東京出張。今日は法政大学にて博物館学芸員資格をもつ大学の会合です。9月の国際博物館会議が終わると、法改正が具体的にスタートする模様。制度を大幅に変えるような意見もあり、またまた振り回されるかもしれません。ただ、会議の中で制度論や職員論については語られますが、利用者の視点がほとんど欠如しているのと、いま博物館が置かれている状況がまるで議論されていない。立派な人材養成はできても、世間から取り残されてしまっては意味ないなぁと思った次第です。議論を聞いていて、なんとなく問題の本質が捉えられていないような気がしました。社会が求める要素が変わってきていると私は考えるのですが…どうなるのでしょうか。そういえば、体調不良はすっかり治りました☆
 │-│-│2019/06/15(土) 23:13│
アラカルト鎮魂振魂の神昨日はなんだか調子が悪いなぁと思っていたら、どうも軽い風邪をひいたようです。今日も一日身体がだるい感じでした。この週末は出張なので、無理しないように気を付けます。さて、また伊勢の話ですが、伊勢神宮に行く前に初めて猿田彦神社を訪れました。この神社には天宇受売命(アメノウズメノミコト)を祀る佐瑠女神社(さるめじんじゃ)がありました。猿田彦命は、滋賀県の?島とも深い関わりがあり、恐らく長寿だったのでしょう。天狗のような姿で描かれることもあることから、私は渡来系の血もひいている可能性があるのではと感じています。天宇受売命は天の岩戸の前で舞を行ったことで知られますが、ここに祀られているということは、猿田彦と結婚をしたのかもしれません。興味深いことに、この天宇受売命は芸能の祖神ということだけでなく、鎮魂の元祖としても祀られています。鎮魂すなわち御魂鎮め(みたましずめ)というのは、「高ぶる心を静め落ち着かせ、穏やかで素直な心の人である様にすること」で、先の祓いの儀式でも行われるわけです。それに加え、「振魂(ふりたま)」を行います。振魂とは、「眠っている力を呼び覚まし、活力あふれる若々しい活動の出来る人である様にすること」とあります。鎮魂はよく聞きますが、この振魂という行為については初めて知りました。少し調べてみますと、この振魂(「ふるたま」とも言うらしい)というのは、武道などにおいても魂を奮い立たせ、身体を活性化させる技として伝わっているようで、身体を小刻みに揺らしながら丹田に気を集める様子がフリー動画などで見ることができます。ヨガとはまた違った面白さがあります。個人的には、学生の眠っている力を呼び覚ますことができればと願うのですが…。あと神社の横に植えてあった招霊(おがたま)という木も気になりました。榊に似ていますが、葉の大きさは二回りくらい大きな感じでした。
 │-│-│2019/06/14(金) 22:13│
アラカルト真経津と二見、精神的の浄化今日もいろいろあって、もうすぐ電池が切れそうです。先日の二見ヶ浦ですが、面白い記録があります。それは偽書とされる『ホツマツタヱ』の中にあり、この地にかつて「真経津八咫鏡(まふつのやたのかがみ)」があったということです。伊勢神宮にある八咫鏡は別名として真経津鏡(まふつのかがみ)とも言われますが、その意味がよくわかっていません。真経津八咫鏡というのは、「人の目には見えない内面の真実を映す鏡」であり、仮の姿と本性との二つの姿を見分ける力をもっているとされています。その二面性を見るという意味で「二見」という地名の由来になっているとのことです。大祓の神である瀬織津姫は、この鏡を万人がいつでも見ることができるよう二見岩(あるいは輿玉神石か?)に置いたとされています。これが八咫鏡の原型となったようで、そう考えると伊勢に八咫鏡があり、なぜここが二見と呼ばれるのかという意味がよく分かります。ただ、ここに真経津八咫鏡は存在しません。また、残念ながら輿玉神石も埋没したまま見ることができません。ところで、「まふつ」という言葉の意味を考えてみると、ここにもある共通点を見いだすことができます。「まふつ」を「ま」と「ふつ」に分けてみると何となく見えてきます。「ま」を「真」とらえ、「ふつ」はよく「ふつふつ」という言葉に代表されるように「湧き上がる」というニュアンスがあります。つまり、「まほつ」は「真実が湧き上がる」→「本性を映す」という意味として理解ができ、単純に言葉から鏡の特性をうかがえるのです。そして面白いことに、この二見ヶ浦は禊ぎの地です。本来は「みそぎ浜」と呼ばれる場所だったようです。この場所は海から押し寄せる波が結構荒く、その強い波で身体を清めたようです。したがって瀧で身を清めることと同じ意味でとらえていたようです。恐らく、自分の身に何か悪いもを見たり感じたりした場合は、禊ぎを行い本来の自分に戻ってから参拝を行うということが当たり前に行われていたのかも知れません。身を清めるというのは、身体だけでなく、心も清らかにするということでもあります。二見ヶ浦では、海水に入って禊ぎをする代わりに、霊草とされる「無垢鹽草」を分けています。無垢鹽草とはこの浜の海中に生息している海草(アマモ)のことで、毎年5月21日の「藻刈神事(もがりしんじ)」で少量採取されたものを使っています。日本の古い信仰というのは、「精神的な浄化」というものを常に考えたシステムのように思えます。祓神である瀬織津姫が不動明王と習合していく背景には、「身を清める」ということと「煩悩を断ちきる」という思想との共通点があったからだと考えられます。
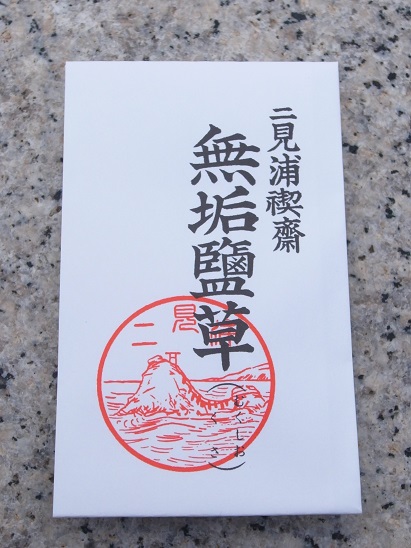 │-│-│2019/06/13(木) 23:27│
アラカルト江戸城再建がスタートやっと晴れました☆雨がないのも困りますが、雨ばかりなのも気が滅入ります。さて、今週のビックコミックで、黒川清作さんの漫画「江戸城再建」が新連載でスタートしました。先月、江戸城再建チームと連携をとったばかりなので、自分の事のように思えます。安土城再建もドラマだらけです。ただ、江戸城再建も安土城再建も一般的には100%無理と言われているような事業ですので、どうなるかはわかりません。個人的な感覚としては、再建が目的なのではなく、前提なのです。再建後の地域振興・地域整備をどうするかを考える方がはるかに大事だと思っています。それは江戸城も同じでしょう。今日のスイーツは、夜に駅前プロジェクトの反省会で学生達と食べたバニラアイスでした☆
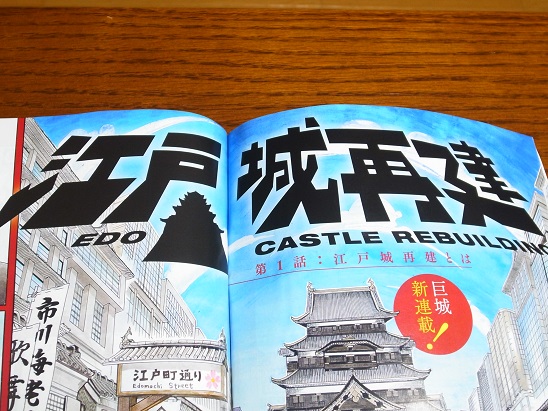 │-│-│2019/06/13(木) 00:15│
|