

Access: |
アラカルト集客するためには滋賀県が昨日発表した情報によれば、「ラ・コリーナ近江八幡」の集客数(延べ受入数)が409万人となったそうです。県内の単独施設で400万人を超えるのは、記録が残る1991年以降初とのこと。ぜひ安土城にも戦国菓子店を開いて欲しい、というか入口にそうした施設を併設した道の駅的なイベント広場にできるといいかも。◆昨夜は甲子園で盛り上がりました。実は、甲子園に入ったのは人生初です。たまたま徳島チームの繋がりでチケットを頂くことができ、観戦してきました。感謝です。両チーム負けられない戦で、阪神の猛打が見られてラッキーでした。このままアレに突き進んでもらいたいものです。この日はお天気も良く、ほぼ満席の42,622人。文化施設の場合、年間4万人に満たない施設も多い中、1日の数値ですから考えさせられます。というか、人の集まる施設やイベントとコラボし、時間帯(待ち時間に利用してもらうとか)やリンクできる内容(スポーツ施設なら医療・健康・力学など)を考えながら、こうしたところに展示施設を設ける必要があると思った次第です。
 │-│-│2024/09/14(土) 09:29│
アラカルトロスフラワーを考える自民党総裁選の候補者が出そろいました。誰がなるにせよ、裏金とかずるするような党員は排除する方向で厳しく運営をして欲しいものです。当たり前のことを当たり前にすることで、社会は良くなるものです。◆昨日は、学生と山科にあるお花屋さん「ちきりやガーデン」さんに伺いました。4回生ゼミのカフェプロジェクトで「ロスフラワー」について連携をとっていただけるとのことで、いろいろと意見交換をしました。普段から環境問題に取り組んでおられるようでとても感心しました。プロジェクト企画の発端がロスフラワーだったので、身近に取り組んでおられるお店に出会えるとは思いませんでした。30年前にいまの店舗を作られたようですが、それまでは御陵にお店があり以前私が住んでいたマンションに近いことが分かり親近感を覚えました。何か面白いことができればと思います。
ちきりやガーデン公式HP https://chikiriya-garden.co.jp/ 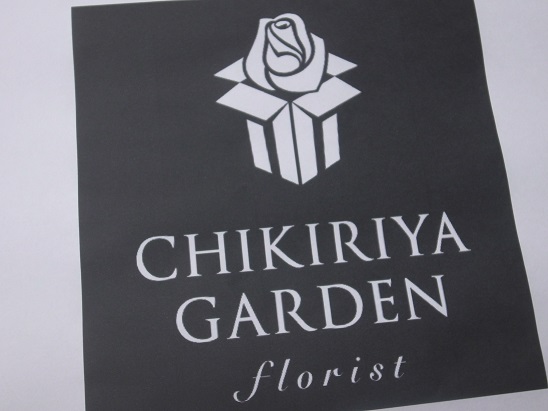 │-│-│2024/09/13(金) 09:24│
アラカルト環境が人の思考を変える世界的人気歌手のテイラー・スイフトさんが、アメリカ大統領選挙候補となっているハリス副大統領に投票すると自身のインスタグラムで表明したそうです。彼女がサイトフォロワー数は2.7億人であり、アメリカの人口(3.3億人)に匹敵する力を持っています。日本ではタレントが政治に口出しするのはタブー的な空気感がまだあり、そういう意味でとても勇気ある行動だと思います。ハリスさんの力量は未知数の部分はありますが、トランプさんが再選されればまた世界は分断されていく可能性が高いと思われます。どうなるのでしょうか。◆今朝、職場の駐車場に行ったら、アオサギが堂々と歩いていました。近づいても逃げる様子もなく、社内からコッソリ撮影。人間よりも目の前の餌なんでしょう。体が少し灰色がかっているのがアオサギです。関東にいた頃は、あまり動物が身近にいる環境ではありませんでしたが、京都は山が近いのでいろんな動物を見ますし、昨日のアオバズクではないですが引っ越ししてからとくに動物に目が行くようになりました。環境は人の思考を変えるのだと思います。
 │-│-│2024/09/12(木) 08:56│
アラカルトアオバズクの声真田広之さんが主演とプロデューサーを務めたハリウッドドラマ「SHOGUN 将軍」が、第76回エミー賞で過去最多の14冠を獲得したとのこと。今後、さらに日本文化への関心が高まっていって欲しいと同時に、次世代に時代劇を知ってもらう意味で、映像製作のあり方がもっと議論されることを期待します。◆森の中で住んでいると、さまざまな動物の声や物音がします。夏の夜中に必ず聞こえてくるのが、「ホゥ ホゥ ホゥ ホゥ ホゥ ホゥ…」と連続する鳴き声です。気になっていろいろ調べてみたら、どうやら「アオバズク」というフクロウの仲間のようです(画像はサントリー「日本の鳥百科」より)。フクロウと思われる鳥もよく来るのですが(うちの辺りのフクロウは「ワン ワン ホッ ホッ」と鳴きます)、夜中なので一度も姿を見たことはありません。ただ、山の中にはほんとに多様な生き物がいるんだということを実感しているところです。
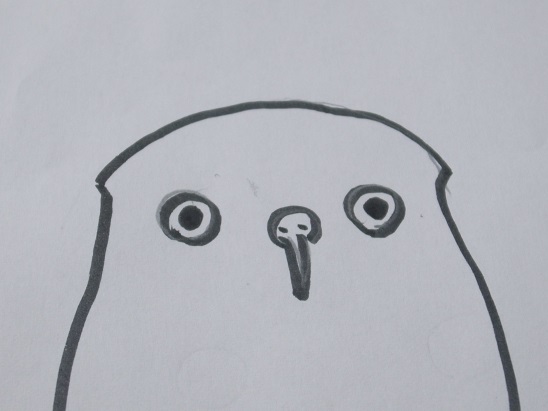 │-│-│2024/09/11(水) 09:49│
アラカルトゼミでカフェを開きますパリパラリンピックが閉会しました。なかり面白そうな試合もありましたがゴールデンタイムにテレビで放送されることがなく残念でした。せっかくの機会なのでもう少し取り上げて欲しいと思いました。なかなか視聴率的に厳しいのでしょうか。◆さて、いよいよ4回生のゼミプロジェクトが形になってきたので紹介をいたします。来月、10月の13日と14日の2日間、山科の椥辻駅から数分のところにあるレンタルキッチンにてカフェを開きます。コンセプトは「もったいない」や「ロス」ということで、広くはSDGsを意識した内容となっています。カフェの名称は「ney-ney project cafe」です。メインはサンドイッチとスイーツと抹茶レモンサイダーで、提携した地元農家さんで育てた食材を使用します。スタッフが使うエプロンは使い古しのジーンズをゼミ生自らがリメイクしたものを使用します。また、店内を飾るお花は、近くのお花屋さんで出たロスフラワーをアレンジする予定です。企画から準備に約2年の歳月をかけてきたプロジェクトです。インスタサイトを始めていますので(予約も開始)、詳しくはそちらをご覧下さい(これも先輩方のサイトを再利用しています)。よろしかったらフォローをお願いいたします。
木下ゼミ・カフェプロジェクトサイト https://www.instagram.com/sdgs_kyototachibana/  │-│-│2024/09/10(火) 08:33│
|